自治会の役員のお仕事の一つに、公園の清掃があるのです。
月2回ですが、公園愛護協会の人たちが毎日お掃除してくれているし、私も練習の前後に、ゴミを見つけたら片づけていますので、だいたいいつもキレイです。
先日は大量のガラス瓶の破片を除去しましたが、そんなイレギュラーなことでもなければ、たいして作業はありません。
私は、落ち葉拾いくらい。他の人は、砂場を均して日本庭園の枯山水みたいに熊手で線を描いていました。
掃除が終わって、せっかく公園に出てきたことだし、ちょっと練習しとくべえと思いまして、模様が描かれた砂場で練習してみました。
自治会役員の皆様、せっかくの作品、崩してすみません。でも、ちょっと試したくなったのです。
それはですね、達人は雪の上で功夫を練っても足跡がつかないということの検証です。
さて、ごらんのとおり。

右から、老架式一路、老架式二路、新架式一路を通した跡です。
まだまだ修行が足りん! というかんじですね。
でもまあ、地面を蹴って砂がえぐれたり、引きずった跡はありませんので、まあまあですかね。
爪先の方向を変える、扣脚と擺脚の跡が目立っております。
安田先生には「上手になったら靴の中で足先がちょっと動くくらいで良い」と習いましたが、そこまでは至っておりません。
ますます精進いたします。
さて、なぜ足跡がつかないのが理想とされているかというと、太極拳の足運びは、猫のように、薄氷を踏むかのごとく、水鳥が歩くがごとく、とされているからです。
地面を踏む反発で体を運ぶのは、お粗末な身体操作ということになります。
虚実変換がスムーズでなく、タイムラグが発生し、反応が遅れたり居ついてしまったりして、武術的に使えないからです。
以前、なんちゃって陳式モドキ太極拳講習会に参加した時、講師が「足を出す時は踵で地面を削るように!」とか「虚歩をグッと踏みしめて体を安定させる!」と説明されてまして、ゲゲゲと思ったものです。
そんな足運びでは、地面はボコボコですね。
というより、靴底の摩擦係数が少なければ、立ても歩きもできまい、ってかんじです。実際、油引き直後の体育館で、この先生、スッテンコロリしているのを、私は目撃しております。
(関係者各位へ。U先生に告げ口しないでください。)
そんなわけで、足運びが正しくできているかのチェックに、砂場とかツルツルの床の上とかで練習してみることをおすすめします。
転倒するかもしれませんが、そこは自己責任で。
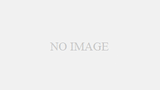

コメント