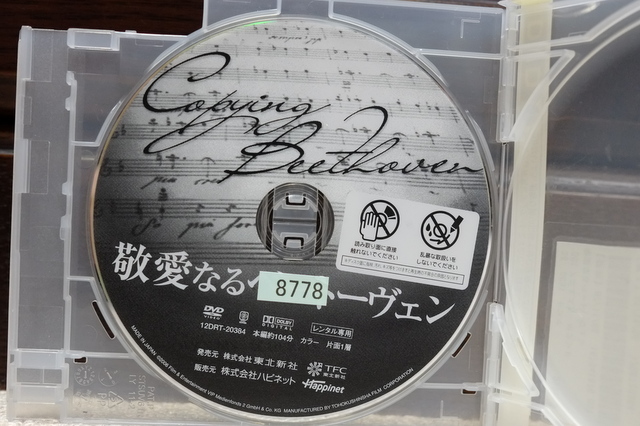
「敬愛なるベートーヴェン」という映画のDVDを、うちの奥さんがツタヤで借りてきましたもんで、私も観ました。
ベートーヴェンがすでに難聴になったあとの話でした。
耳の聞こえないベートーヴェンがどうやって作曲していたのかは、私も昔から関心があったので、興味深く鑑賞させていただきました。
目次
敬愛なるベートーヴェンのあらすじ(ネタバレあり)
交響曲第9番の公演が4日後に迫っているのに、まだベートーヴェンの譜面ができあがっていない、しかも馴染みの写譜師(楽譜の下書きを清書する人)は年老いて病気で、もう無理、という状況であり、急遽代わりに呼ばれた写譜師が、作曲家を目指す23歳のアンナ・ホルツ(ダイアン・クルーガー)という、美しい女性でありました。
ボロアパートのゴミ溜めみたいな部屋に独身の一人暮らし、わがままで言いたい放題、女性蔑視の頑固爺の、人格的にはかなり破錠したベートーヴェン(エド・ハリス)が、最初は、女なんぞアカンと言ってたんですが、なんだかんだあってアンナを認めて、第九番を完成させます。
公演ではベートーヴェンがオーケストラの指揮をするのですけど、もう耳が全然聞こえてません。
観客のつもりで来ていたアンナが、思い立って楽団の間に潜り込み、ひそかに手を振ってベートーヴェンにサインを送ります。ベートーヴェンはそれを頼りに指揮棒を振り、公演は感動的に大成功となったのでありました。
その後、ベートヴェンの作曲や芸術感は、さらに神がかってきて常人の理解を超えるようになります。
アンナの恋人の設計士がコンペのために作った、ドナウ川に懸ける巨大橋のモデルを、「魂がこもっとらん」とぶっ壊し、アンナの作曲した曲も、オナラの歌だとこき下ろしてしまい、アンナを落ち込ませてしまいます。
なんだかんだあって思い直したベートーヴェンは修道院に突入してまでアンナを迎えに行き、アンナの作品を二人で完成させます。
しかし、最後の自信作の弦楽四重奏「大フーガ」は前衛的過ぎて、聴衆には全くウケず。公演後に倒れて、芸術家としての最後の活躍は締まらないものとなったのでした。
ラストは、ベートーヴェンがベッドの上で作曲した、長調でも短調でもない賛美歌のような旋律をアンナが採譜していくシーンです。
ここではピアノを弾いたり歌うのではなく、ベートーヴェンが音符や休符を語り、それをアンナが書き留めていきます。
実際の音は鳴っていないわけですが、二人の頭のなかでは同じ音楽が流れており、ベートーヴェンは幸せな気分で天国に導かれたのでありました。
敬愛なるベートーヴェンの見どころ
ハイライトのシーンは、やはりアンナのサインを頼りに、耳の聞こえないベートーベンが指揮棒を振っているシーンでしょう。神がかっていて、なかなか感動的で、ここは泣くところです。(現実的には絶対無理!という意見もあるようですが。)
ところで、第九というと年末によく聞く合唱ですが、あれは交響曲の一部分であって、フルバージョンで聞くと2時間くらいあるそうですね。それだけで映画が終わってしまう長さです。
一度は生の演奏を通して聴いてみたいものです。(たぶんそんな日は一生来ないような気もしますが。)
私が知りたかった、難聴のベートーベンが作曲しているシーンでは、巨大な補聴器をつけて、頭の後ろには手作りっぽい音響反射板をつけてピアノに向かっておりました。
何かの読み物で、指揮棒をピアノにおしつけて骨伝導で音を判別していた、というようなことを読んだのですが、そういうシーンは映画ではなかったです。
本当のところはどうだったんでしょうね。
敬愛なるベートーヴェンの感想
実は、この映画のヒロインのアンナは、架空の人物だそうで、実話だと思ってみていたので、一気に興ざめしてしまいました。
ベートーベンの写譜師というのは実際に何人かいたそうですけど、そんな23歳の美人というわけではなかったようです。映画を面白くするための設定ですね。
ですのでドキュメンタリーじゃなくって、史実を元にしたエンターテイメントだと思って観たほうが良いです。
邦題は「敬愛なるベートーヴェン」なので、ベートーヴェンに憧れ慕う人の物語なのかと思ってしまいますが、原題は「Copying Beethoven」です。
ベートーベンを写譜する、というくらいの意味になりますね。
写譜師という、あまりなじみのない立場から、ベートーヴェンの人物像や心情をとらえてみました、というふうに観たほうが、監督の意図を理解しやすいのではないかと思います。
私の感想は、やっぱり芸術家って変人なんだな、ということでありましたが、音楽家は神と一番近いのだ!という説得には、唸るものがありました。
聞こえない孤独とか恐怖、という部分の描写は、あまり出しきれてなかったんじゃないかなという気はします。(聞こえていたときから孤独だったのでしょうけど。)
手塚治虫のマンガでは、そのあたりの苦悩をもっと描いていたような気がしますが、この映画のポイントは、そこではなかったのかもしれません。


コメント