太極拳の講習会と言えば、以前、「対練」の講習会に参加したことがあったなあと、思い出しました。
そちらでは同じ教室の人や、近隣の教室の見知った顔の人が大勢参加しており、和気あいあいと楽しい講習会でした。
その時の様子は、このブログにも書いております。
太極拳に対練套路があるということは、その時に初めて知って感心したんですが、ちょっと疑問に思ったことも書いておりました。
あれからもう7年になりますが、今振り返りますと、やっぱり対練套路には疑問があります。
早い話が、いらんのとちゃうか?という気がするのです。
実は来月、太極拳の発表会があり、推手道場のメンバーも出場することになりまして、発表の演目を練習しております。
以前、アトラクションとして、舞台上で自由自在な推手をさせてもらったことがありますが、発表会であまりに無秩序なのも見苦しかろうと、8人ほどが同じ動作をするように組み立てています。
推手を知らない人たちに、推手ってこんなもんだよと見せるためのものです。デモンストレーションです。
こちらのメンバーでやるのは、ごく簡単な動作の組み合わせですが、套路の動作を組み合わせて複雑にして形通り順番通りに動くのが「対練套路」でありましょう。
一人で行う型練習が套路、それを二人でやるのだから、いい練習じゃないか! とも思えましょうが、いやあ、どうかなあという気がするのです。
一人套路の場合は、動作の意味解釈は無限であり、変化も無限です。
しかし、お互い打ち合わせ済みの対練套路にしてしまうと、動作が固定されます。
違うことをしたら、「ちゃうがな! こっちや、こっち!」「ごめん、まちごうた」みたいに小声でヒソヒソつぶやいたりして、なんだか本質から外れていくような。
ものすごく練習をして、息もぴったり、一糸乱れぬ見事な演武となったとしても、それ、使えるか? という気がするのですよねえ。
そう思うのは、少林寺拳法修業時代、散々やってきたからです。組演武、どれだけすばらしくできても、乱捕りとは別物です。
学校のクラブによっては、演武要員、乱捕要員とわかれてたりして、違うものになってるところもありました。
組演武でできたことが、乱捕では通用しません。乱捕りで培ったテクニックも組演武には使えませんでした。こんなんなんぼやっても、しゃーないなーと心の片隅で感じておったのです。
太極拳の練習方法には「推手」があります。推手と対練は同じように見えるというか、推手をカッチリしたものが対練に見えます。
自由にやっている推手が、まるであらかじめ組まれた演武に見えるというなら、大したものだと思いますが、あらかじめ組まれた対練ばかり上手になっても、自由な推手ができるかどうか?
先日の安田先生とのデモンストレーションは、まったく打ち合わせなしで突然始まったものでしたが、動画を見たら、あたかも用意してきたもののようにも見えました。まあ、安田先生がリードしてくれてたんですけど。
そのレベルに近づこうと思えば、まずは基本を練って、一人套路で太極拳の動きをすっかり身につけ、そして推手で対人感覚を養っていくという順番になるかと思います。
あらかじめ決まった動作の対練套路をなんぼ練習していても、相手が変わったらできないとか、急に振られたらできないとか、そんなんじゃ意味ないですね。
というわけで、デモンストレーション目的でなければ、対練套路はいらんかなあと思ったのでした。
そういえば、今後予定されている陳氏太極拳カリキュラムに、対練は入ってなかったなあ~と、今、気づいたのでした。
7年前の記事
↓
>>太極拳に対練があると初めて知りました

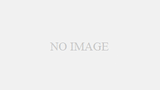
コメント